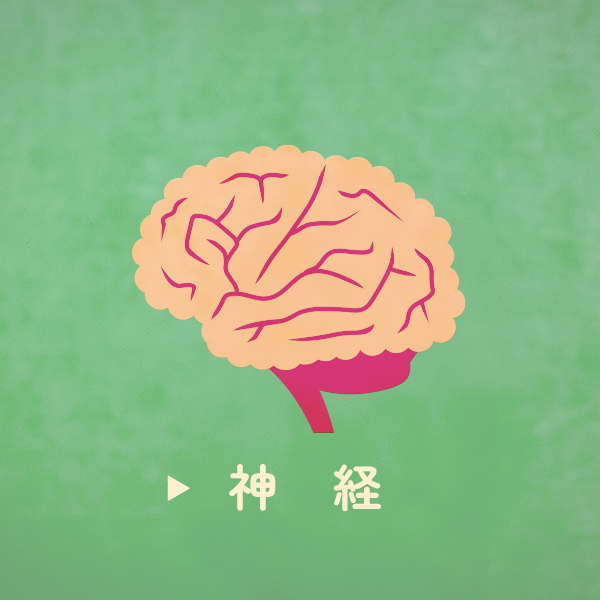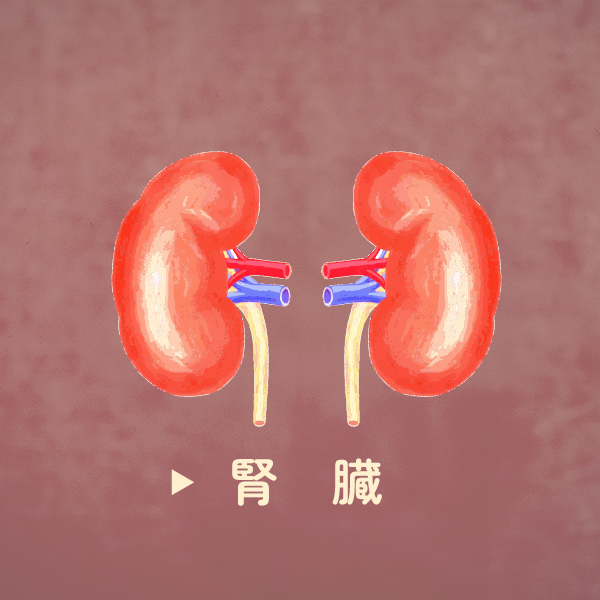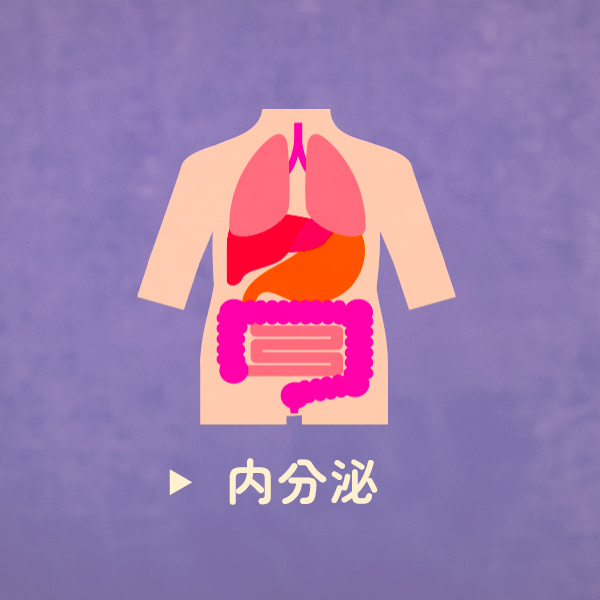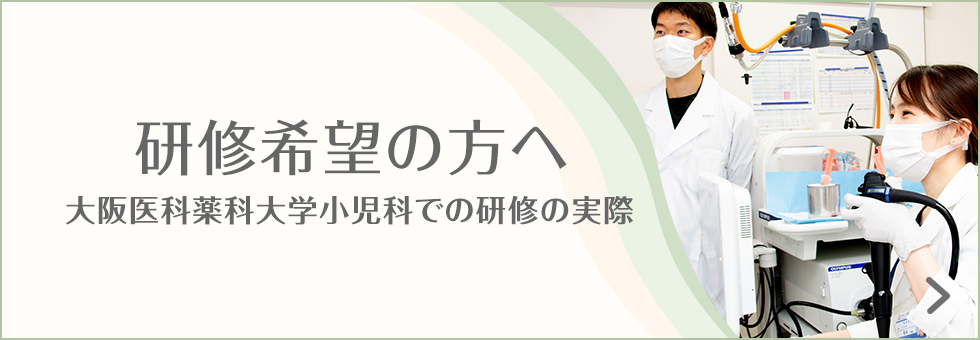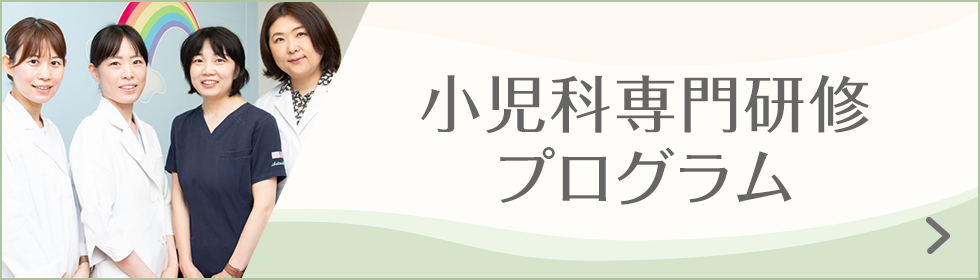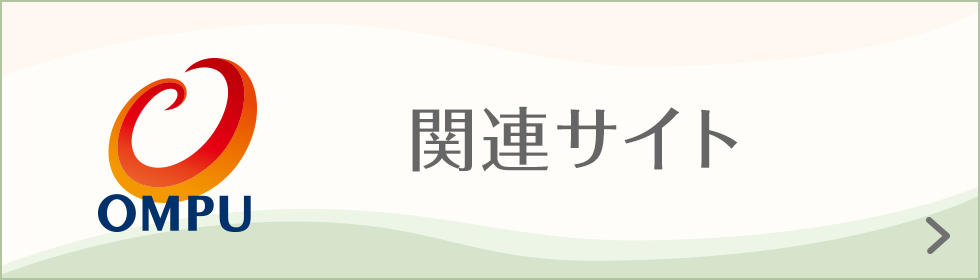大阪医科薬科大学小児科神経グループで発達・小児神経疾患の診療を学び、こどもたちやその家族から必要とされる専門医をめざしませんか?
大阪医科薬科大学小児科神経グループで発達・小児神経疾患の診療を学び、こどもたちやその家族から必要とされる専門医をめざしませんか?
小児神経疾患のお子さんはひとりひとりが稀少疾患のお子さんであり、重症度も治療も一人一人異なり、疾患の情報の少なさに困っているご家族がいます。また一方で、神経発達症/ 発達障害のお子さんは、診断が同じでも困りごとが異なり、その困難をうまく相談できず、インターネットにあふれる情報に踊らされどうしてよいのか答えも得られず困っておられるご家族がいます。われわれは、このような日常生活・社会・学校への適応が難しいお子さんたちひとりひとりと密にかかわり、ご家族に寄り添いながら、こころとからだの健康を一緒に目指します。小児神経領域は、小児科臨床医として必ずやりがいを感じることのできる領域です。
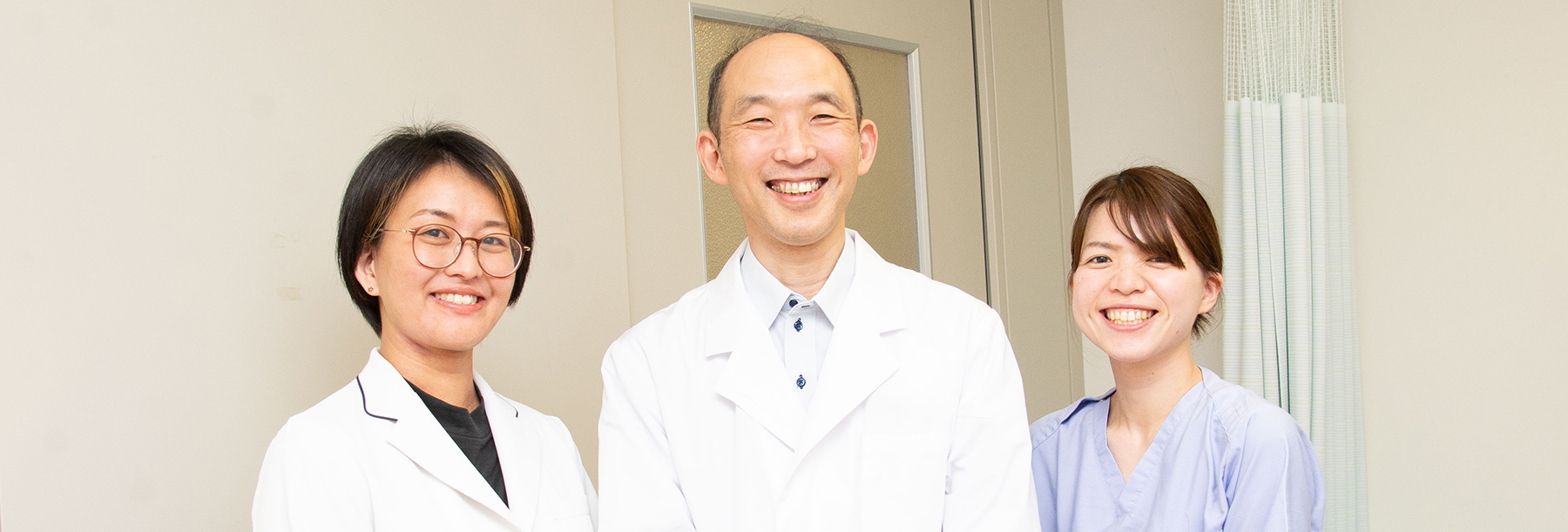
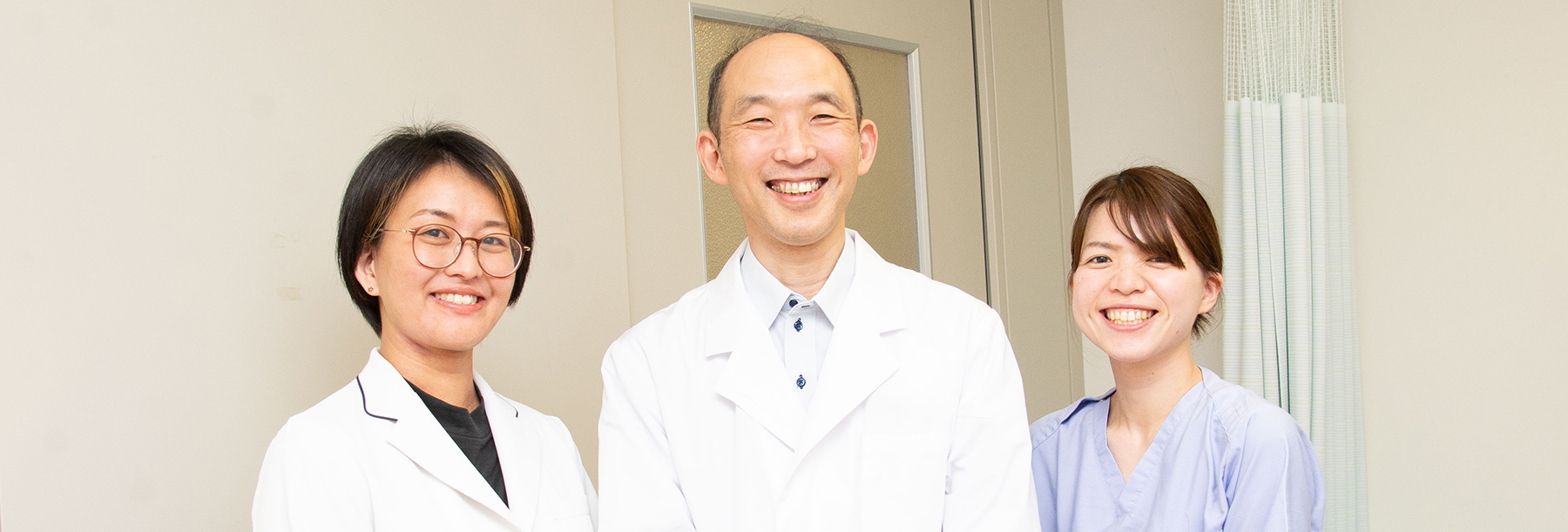
今、小児神経学は近年めざましい進歩を遂げている領域です。筋ジストロフィー症、脊髄性筋萎縮症の治療薬の保険適応が記憶に新しいですが、従来不治の病とされた病気にも治療の可能性がでてきており、若い先生にも希望をもって取り組める分野ではないかと思っています。また、インターネットやSNS の発達から、希少疾患の治療法についても社会の認知度が高まり、注目されてきています。こういった現代の診療、研修とはどうあるべきなのか答えはありませんが、当科ではスタッフ間で忌憚なく意見交換があり、真摯に患者さんと向き合える環境になっています。
現在、子育て中で時短勤務の先生も在籍中です。静岡てんかん・神経医療センターや岡山大学への国内留学の経験がある先輩や、クリニックを開業する先輩たちもいます。ご自身のキャリア形成について、先輩たちといろいろ相談も可能です。随時見学にいらしてください。
スタッフ
島川 修一
1995年 大阪医科大学卒
大阪医科薬科大学 小児高次脳機能研究所 特務教授
日本小児科学会小児科専門医•指導医•評議員
日本小児神経学会小児神経専門医•指導医•評議員
日本てんかん学会専門医
北原 光
2012年 大阪市立大学卒
大阪医科薬科大学病院 中央検査部助教
日本小児科学会小児科専門医•指導医
日本小児神経学会小児神経専門医
日本てんかん学会専門医
居相 有紀
2018年 川崎医科大学卒
大阪医科薬科大学 小児科 大学院生
福井 美保
2003年 大阪医科大学卒
大阪大谷大学 教育学部 教授
日本小児科学会小児科専門医•指導医
日本小児神経学会小児神経専門医•指導医•評議員
日本てんかん学会専門医•指導医•評議員
柏木 充
2000年 大阪医科大学卒
非常勤講師 市立ひらかた病院 小児科 主任部長
小児科専門医•指導医
小児神経専門医•指導医•評議員
てんかん専門医•指導医•評議員
日本小児救急学会代議員
日本 DCD(発達性協調運動障害)学会理事
大場 千鶴
2008年 大阪医科大学卒
市立ひらかた病院 小児科 部長
日本小児科学会小児科専門医
日本小児神経学会小児神経専門医
日本てんかん学会専門医
鶴長 恵理子
2013年 高知大学卒
大阪府済生会吹田病院 小児科 医員
國貞 佳世
2003年 福岡大学卒
清恵会病院 小児科 医員
日本小児科学会小児科専門医
中西 苗穂子
2016年 川崎医科大学卒
市立ひらかた病院 小児科 医長
日本小児科学会小児科専門医
山本 千裕
2022年 大阪医科薬科大学卒
大阪府済生会吹田病院 小児科 医員
研究内容


神経疾患全般
小児神経疾患のお子さんはひとりひとりが稀少疾患であり、難病です。個々のお子さんの診療から、新しい知見を見いだし、学会発表・症例報告・論文作成しています。小児神経専門医研修認定施設であり、研修後、てんかん学会専門医が取得できます。


神経発達症
最近の発達障害への注目度の高まりから、神経発達症の診断、治療を正しくできることは小児神経医の重要な役割になりました。当院は、限局性学習症/ 学習障害と正しく診断できる全国でも稀少な施設です。われわれは、学童期神経発達症の学習困難や限局性学習症/ 学習障害の診療と研究をおこなっています。これらの診療および研究は、LD センター、小児高次脳機能研究所と密に連携して行います。
診療では、それぞれのお子さんの学習困難の脳内機序を分析し、結果から導かれた学習支援方法をお子さんやそのご家族に提案しています。研究では、文部科学省科学研究費を取得し、学習困難の背景にある認知的特徴をテーマとした研究を多数行っています。大学院生も所属しており、論文指導、学位取得も可能です。
医療関係者向けに限局性学習症/ 学習障害の診療や対応をテーマとしたセミナーを年1 回開催しています(LD 診療セミナーベーシックコース・LD 診療セミナーアドバンスコース)。そちらも是非ご参加ください。
LD センターホームページもご参照ください。


超早産児の認知機能
超早産児において、発達障害の発症率が高いと言われていますが、幼少期の発達検査で正常範囲内といわれていても就学後に問題が生じることも多く、見逃されていることが少なくありません。超早産児のお子さんたちが幼児期、学童期になられたあと相談に来ていただける相談外来もLD センターで行っています。
超早産児は、正期産児にくらべて脳細胞や神経ネットワークに違いが生じている可能性が報告されており、発達障害と診断されるお子さんの割合やその症状にも少し違いがあるのではないかと議論されています。大阪医科薬科大学では、超早産児の認知機能の解明に取り組んでいます。今現在は、文部科学省科学研究費を取得し、超早産児の視覚情報処理能力に着目した研究をおこなっています。


てんかん
てんかんにおいては、MRI、SPECT、PET などの機能画像検査に加え、ビデオ脳波同時モニタリング装置を用いた診断と治療が可能です。救急応需率の高い病院のため、けいれん性疾患の症例は多数経験できます。
臨床での知見を、学会発表・症例報告・論文作成しております。てんかんの包括的な診療にも目を向け、てんかんをもつ児の認知行動の解析も行っています。日本てんかん学会の研修施設であり、研修後、てんかん学会専門医が取得できます。
小児医療を目指す皆さんへ
当院は、救急疾患応需率が高いため、急性期の神経疾患(けいれん重積症、急性脳症など)の診療も経験できます。また、神経発達症/ 発達障害の紹介数は多く、限局性学習症/ 学習障害は全国から多数の相談がありますので、十分に経験を積むことができます。